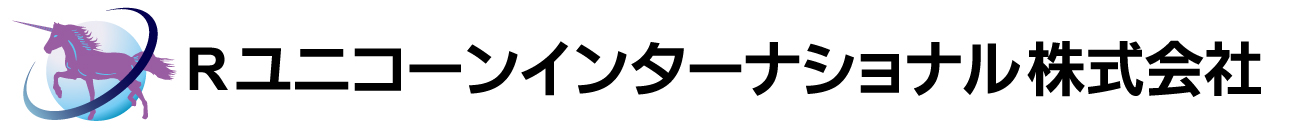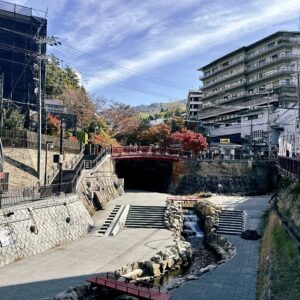将棋の魅力 <静の真剣勝負の中で垣間見える闘志>
最近、非常に関心のあることの中で、主にタイトル戦と称される将棋の対局のAbema等での生観戦があります。
将棋は小さい頃少しやったことはありましたが、一向に強くならず途中で止めてしまいましたが、それでも駒の使い方を含めて囲碁同様に少し関わったことがありますが、野球と比較すれば打ち込み度合いは極端に低く、結局それ以来あまり関わることがなかったのですが、、、
ところが、ある時、名人戦だったか、今この将棋界でトップに君臨している23歳の藤井聡太棋士の対局中継を目にする機会が偶々あり、退屈するどころか何か将棋の対局時に醸し出される「静の間の空間」に魅せられてしまったことが、最近将棋の対局中継を見るようになったきっかけになります。
竜王戦や名人戦ともなれば、対局も2日掛かりになり、各自の持ち時間も8時間とか9時間になります。時として長考という時間があり、60分から120分、考え続ける時間が出てきます。その間、画面上では、何十手先の棋譜を真剣に読む棋士の姿が映し出され、何度も席を外したり、正座から胡座に切り替えたり、髪の毛を掻きむしってもがき苦しむ姿が時として目に入ってきます。
以前は、そのような長考の時間は、「何て退屈な映像なんだ」としか思っていなかったのですが、最近「この静の格闘時間の魅力が面白い」と思うように変わってきました。これも年齢の成せる業ではないかと思います。
私は小学生の頃から野球に真剣に取り組んできたことからもお分かりの通り、スポーツ全般の生観戦が特に好きです。野球に限らず、試合の現場に赴き、そこでの臨場感と生で受ける感覚がとても刺激的で、テレビでは体験できない貴重な瞬間を堪能できます。
確かに将棋や囲碁はスポーツというジャンルには属しませんが、目の前の相手を倒す、相手に勝つということは一緒です。格闘技という言葉はスポーツの世界だけに適用されるものと以前は思っていましたが、紛れもなく将棋や囲碁も目の前の相手を倒す(相手の王の駒を詰ませる)ことのみが目的であって、知能を使った格闘技だと思えるようになってきました。しかも静の空間で格闘しているところに、一種の魅力を感じます。
そして、最後に将棋中継を見ていますと、最後の終局の場面で、片方が参りました、負けました、と宣言して、静の格闘技が終了します。所謂試合終了です。ところが、野球では考えられないことが次に起こります。それが「感想戦」です。

真剣勝負が終わり疲れ切っているところで、対局者2人での反省会が開かれるのです。
「この場面で色々な選択肢があったのですが、自分の指した手ではなくて、2番手、3番手に考えていた手を披露して、その後の展開を実際にやってみるというものです。「実はこちらの方が効果的な手であった、やはり自分の指した手が最善手であった」などなど、いわば非常に高いレベルでの反省会、勉強会のようなものを結構延々と公開の場でやるのです。
これは野球には絶対にないことです。野球はそもそも個人プレーではなく、チームプレーではありますが、例えばサヨナラホームランを打った打者と打たれた投手が、試合終了直後に直接言葉を交わす場面は想定できません。しかも、「あの時、初球をストレートではなく、変化球(フォークボール)から入っていればもしかしたら打ち取れたかもしれない」など、自分の手の内を相手に見せるような行為は、例え試合終了後だったとしても絶対にしないはずです。
その意味で、将棋は凄いと思いました。より高い位置、たかみを目指して、精進を続ける、その為には終わったばかりの対局をすぐに当事者同士で振り返る、そんな正々堂々とした静の格闘技なんだと、改めて実感しました。勿論、棋士の中には、本音を漏らさずに上辺だけでやり過ごす棋士の方もおられるかもしれませんが、対局後の疲れ果てた状態で、しかも負けた相手と反省会を開くというのは、結構精神的には堪えるように思います。
奥の深い格闘技、静寂の中に眠る心の中に潜む闘志が垣間見える、そんな将棋の魅力に最近のめり込みつつあります。
そして、近い将来、将棋対局を生で観戦してみたいと、本気で思うようになりました。そんな瞬間が訪れることを願って。
最近将棋好きなリスク管理コンサル 髙見 広行