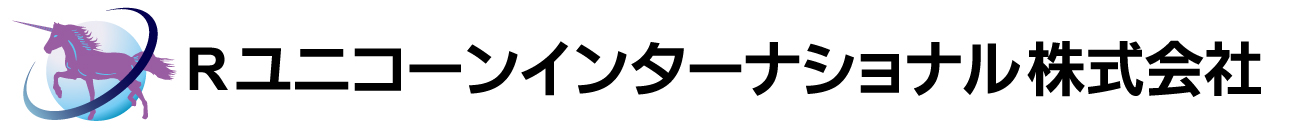富士山の麓に佇む「富士錦酒造」様を初訪問!
皆さん、8月も下旬に差し掛かっておりますが、暑さの勢いは衰え知らずで、まだまだ猛暑は暫く続きそうです。
そんな中、かねてコロナ禍の時期より私の知人を介して訪問を計画しておりました静岡県富士宮市の山間部に位置する富士錦酒造様を、遂に先日1人で訪問する機会を得て、実際に行って参りました。当日は蔵内は「マルシェ」という市場が何軒か開設されていて、野菜や飲み物等のジュース、また地元名物の富士宮焼きそばの屋台まで出店していて、賑わいを見せていました。












当然、富士錦酒造様の醸すお酒も飲めるコーナーが設置されていて、実質生まれて初めて富士錦酒造様の日本酒を口にすることができました。酒の感想は、実に酒米の旨味を全面に出したようなコクのあるお酒で、富士山からの湧き水のせいか、飲んだ後にスッキリ感を感じます。癖のない飲み易いお酒です。静岡県もまた秘蔵の日本酒が眠っている場所だと実感しました。
場所は、新幹線の新富士駅から車で小1時間程富士山方面に向かって走り、山間に位置する静かでひっそりと佇むイメージで、富士山から湧き水を仕込み水にされている恵まれた環境にあります。訪問当日は残念ながら富士山の姿を拝めませんでしたが、冬などは綺麗に間近に富士山を鑑賞できる絶好の場所にあります。
富士錦酒造様は、元禄時代(1688~1704)に創業している歴史の古い酒蔵様です。しかしながら、創業当時から現在の造り酒屋の姿ではなく、元々は地元の地主として、小作人を数多く雇うほど大きく農業を営んでいたようです。当時、小作人からもらう小作米が多く入ってきた為、そのお米を用いて酒造りを行った事が、今の姿となるきっかけでした。
当時は売る為の酒造りではなく、小作人への褒美として、また当時は現在のような娯楽が少なかった為、唯一の楽しみであった秋祭りに奉納する為の御神酒として、お酒を少しだけ醸造していたそうです。その後、戦後の混乱時期に、農地改革(1946)により農地の大半を失い、それまで副業で行ってきた酒造りを、これを機に本業としたのでした。本当に歴史の変遷を肌で感じますね。
同酒蔵の第18代目の蔵元である清 信一様とも、訪問当日、初めて挨拶を交わし(名刺交換も行う)、短時間ではありましたが直接お話する貴重な機会を得ることができました。記念撮影も行わせて頂きました。とても温厚そうで、人間味溢れる方のように見えました。また、個人的に関心を惹かれるご経歴の持ち主で、また改めてじっくりとお話をしてみたい方であると感じました。
現在も酒蔵の周囲に農地を自社で保有され、酒米を造られているようです。現在の生産石数はおよそ1,000石、ピーク時は2,000石は生産されていたと言います。蔵元の奥様に酒蔵案内をして頂き、じっくりと内部を見学させて頂きました。勿論、周囲の農地も見学させて頂きました。自然たっぷりの長閑な場所で、都会の喧騒を忘れたい方は絶対にオススメの場所です。
4月には酒蔵びらきのお祭りイベントが行われるようです。来年は是非とも訪れてみたいと思いました。
今回の新しい出会いに感謝しながら、富士錦酒造様を後にしました。
秘蔵の日本酒 高見酒店
店長:唎酒師タカミン(髙見 広行)