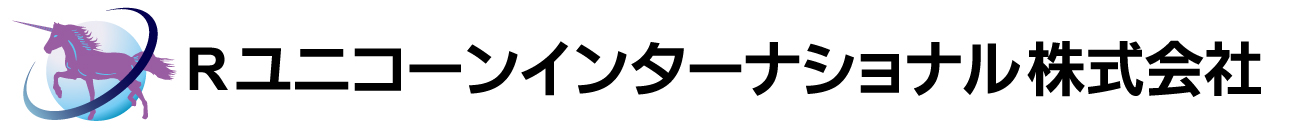兵庫県の2大巨頭の温泉地の比較検証!
私自身、還暦を来年に控えて、最近とみに「温泉」への憧れというか、休息の場としての日本伝統の場所に対する存在価値を改めて強く実感することが多くなりました。
元々、温泉大好き人間ではありましたが、ここ1年位で更にその想いは高まってきているように思います。日頃の疲れが溜まっているからでしょうか?、それとも年齢相応の年輪を重ねたことによる金属疲労が生じてきているからでしょうか?脱サラして自分の力で会社を支えていかなければならないという暗黙のプレッシャーを感じているからでしょうか?
上記全てが温泉に惹き込まれる要因になっているように思いますが、とにかく心が落ち着く場所、休息できる場所、という結論に達します。
家でもお風呂を沸かして入ることはありますが、やはり真の温泉の湯の質には全く及びません。日本各地に散在しているこの日本伝統の文化を醸し出す場所、それこそが海外の方々からも最近脚光を浴びつつある「日本の温泉」なのです。
さて、そんな中で、私自身の理解においては、関西の兵庫県にある2大巨頭とも称される温泉が、「有馬温泉」と「城崎温泉」になります。
今日はこの2つの温泉を実際に訪れてみて感じたことを私的な意見で気ままに語らせて頂きます。
まずは、あの太閤殿下がこよなく愛した温泉として有名で、神戸の奥座敷とも呼ばれる場所にある「有馬温泉」について、私見を語らせて頂きます。
有馬温泉との本格的な出会いは今から6年前の2019年12月の年末に遡ります。家族3人で初めて有馬温泉を訪れ、地元では大手ホテルの有馬グランドホテルに宿泊、実に快適な滞在を送らせて頂いたことが始まりです。何故、その時有馬を選んだのか、それには一つ大きな理由がありました。それは日本酒ビジネスを手掛けるべく個人起業を目前に控えて、兵庫県の丹波地方にある酒蔵様を訪問するに当たり、その酒蔵様の紹介者である知人で当時ニューヨーク在住の方が車で案内・同行して下さるということで、合流場所として有馬温泉に決まったという経緯があります。本当に巡り合わせというのは不思議なもので、それ以降、最近では有馬温泉に足を踏み入れる機会が多くなりました。
有馬温泉の特徴は、源泉に大きく分けて2つの種類があり、それが金泉と銀泉という全く異なる湯質の温泉を同じ場所で体験できることにあります。金泉は弱酸性湯で見た目は土色の硫黄臭を感じる温泉です。他方で銀泉は透明色でアルカリ性の一般的によく見る温泉です。私は個人的に前者の金泉の方が好きで、絶対に金泉の方から浸かることにしています。体の芯まで温まるという表現がぴったりの湯質で、飽きることなく浸かっていることができます。
そしてもう一つ有馬温泉の持つ魅力は、アクセスの良さにあります。新神戸駅から電車で乗り継いでいけば30分強、勿論バスも出ており、新大阪駅からもリムジンバスが出ており所要時間は約1時間弱。東京から新幹線で行けば意外と所用時間は短いのです。又伊丹空港からもバスが出ており飛行機で行ってもそれ程時間は掛からないのです。神戸の裏側にあるひっそりとした自然溢れる山間の場所でありながら、神戸からは通勤・通学できる距離にあるのです。
温泉街の雰囲気は、中心部に小道があり、坂を登っていく通りの両側にはお土産店や飲食店等が立ち並びます。ただ、規模は然程大きくはなく小ぢんまりとした印象です。コンパクトな規模で、山間の谷間に温泉街があるという印象で、これは最初意外に感じる人も多いかもしれません。私がよく訪れる鉄板焼き屋さん「一休」があるのもその温泉街の小道の通り沿いにあります。







次に、「城崎温泉」について触れてみたいと思います。
実はこの温泉にはずっと行ってみたいという想いはあったのですが、中々実現の機会がなく、漸く今年になって出張場所との兼ね合いで幸運にも初めてこの有名な温泉地を訪れることができました。こちらは、有馬温泉とは正反対の兵庫県の北部、日本海側に近い場所にあり、アクセス面は正直あまり良くありません。東京から行きますと、京都駅まで新幹線で2時間20分位かけて移動して、その後京都駅で特急電車「きのさき」に乗り換えて2時間30分前後。即ち、トータルで5時間前後は掛かるということになります。
温泉の湯質は、透明色のアルカリ性のお湯で、所謂王道とも言える典型的な癖のない湯質だと理解しています。いつまで入っていても飽きない、やはり知名度のある日本を代表する温泉地であることを実感しました。
城崎温泉の最大の特徴は、駅を降りてから街全体が大きな温泉旅館の敷地内という気分にさせるような一体感を強く感じることです。また有馬とは異なり基本平地で移動しやすく、通りの広さもそこそこ余裕があり、ゆったりと歩いて外湯めぐりができることが特徴です。勿論、宿泊旅館の中にある温泉も内湯・露天風呂共に素晴らしく、外に出ても外湯があり、居酒屋・飲食店・お土産店も多く、飽きさせない街づくりが実現されています。日本酒好きの私に特に響いたのが酒屋さんの数が多いこと、中には角打ちスタイルで立ち飲みができるスペースがあって、温泉巡りの途中で軽く一杯やりながら昼間からいい気分になれることが嬉しい場所ですね。











以上、兵庫県を代表する2大巨頭の温泉地について今回触れさせて頂きました。
温泉マニアとしてはこの2つの温泉地はやはり外すことができません。兵庫県の北と南に存在するこの温泉地、共に個性があり、存在感があると感じました。日本文化のど真ん中にある温泉文化、それと地酒/地魚等とのコラボで、訪れる度に気分は盛り上がります。
また今後機会があれば、訪れた温泉地について勝手気ままに語らせて頂きたいと思います。
今回は最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。
温泉マニアのリスク管理コンサル 髙見 広行