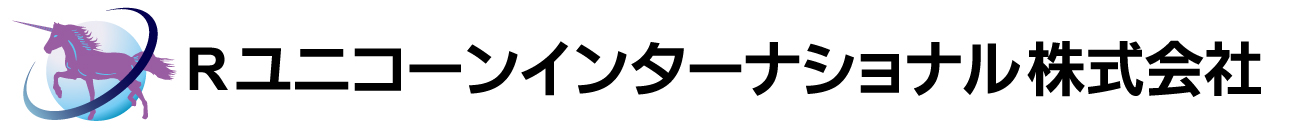どうなる今後の都市銀行!揺れる銀行ビジネスモデルを考察
最近ある大手都市銀行の都内にある大手支店を何軒か訪れる機会を得た。
バブル入社組の私にとっては、あの頃の光り輝く都市銀行の姿が脳裏に焼き付いている。就職人気ランキングで常に上位に位置していた銀行様である。
ところが、である。
率直に申し上げて、最近の都心部かつ駅近主体の店舗設営のビジネスモデル自体が、時代の流れに大きく取り残されているように見えて仕方がない。
足元での業績が良いということで実態が隠れてしまっているように見える。
例えば、店舗に纏わる重い重い家賃負担の改善、今後の店舗経営スタイルを踏まえた従業員の余剰問題についての対応策等、目先の経営課題のハードルは極めて高いと見ています。我が国のメガバンクが果たして今の状態のままで、存続し続けることができるのか、大いに疑問に感じる。
未だに、午後3時で窓口業務が閉まるスタイルを踏襲、明らかに利便性という意味では、ネットバンクとの差が出始めている。店舗によっては21時まで窓口営業を行う、土日祝日でもオープンする店があっても決しておかしくはないと思う。更に、平日に窓口に行っても結構待たされる、事前に予約して行かないと待遇面でやや落ちる印象を受ける、こんな印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?
挙げ句の果てに、様々な両替業務にも手数料を課すようになった。しかも幼い子供やお年寄り等が手元に貯めた小銭を両替する際にも、一律に手数料が掛かるようになった。更には、店舗の事情により、法人業務の取り扱いを突如休止し、急遽隣の駅の支店を案内される等、自分が接している都市銀行のサービス内容が、利用者目線でみて明らかに期待から外れる内容になっていると指摘せざるを得ない。
コロナ時代を経て様々にサービススタイルを変更せざるを得なかったのは仕方ないことにしても、それにしても今のやり方が私には正しいスタイルにはどうしても見えない。もしこのままのやり方を続けていくとしたら、本当にこの先10年後、20年後に、都市銀行が生き残っていられるのかどうか、疑問に思わざるを得ない。
他方で、以前ニュースでも結構騒がられていたが、貸金庫サービスを悪用しての行員による窃盗事件という前代未聞の大事件まで起こしている有様を見ると、本当に都市銀行が今顧客の為にきちんと機能しているのか、改めて世の中からその存在感を問われていると言わざるを得ない。
このような環境の中で、果たして日本の都市銀行がどのような新しいビジネスモデルを構築して、生き残りを図っていく道を模索していくのか、個人的に非常に関心がある。今こそ、思い切った大転換を実行する時に都市銀行は直面しているのではないか?
そして、最後に追加で申し上げたいのは、私が商社在籍時代に、何度も何度も債権保全の場面で目の前に登場してきた都市銀行を含む銀行という大きな存在である。常にフル担保をベースに考え与信を供与していたスタイルに、個人的には強い嫌悪感を感じていた。常に、商社は銀行の後順位での担保設定に甘んじざるを得ず、苦汁を嘗めてきた経緯がある。
バブル経済崩壊後に銀行が取得していた不動産担保の担保価値が大きく下落し、取引先の倒産と共に多額の焦付きを蒙る事態に直面、そしてその後の経済情勢を受けて、破綻する金融機関が続出し、金融機関の合従連衡が進み、銀行の数が減って一気に淘汰されていったという事実がある。
ある有名なテレビドラマで、「銀行は晴れの時には傘を貸すが、雨の時には傘を貸してくれない」というようなフレーズが登場していたが、まさに銀行の融資姿勢そのものに対する核心を突く問題指摘だと認識している。
銀行による融資実行時の審査業務(与信管理)は、今も尚、世の中において重要な役割を果たすものであり、是非とも、この切り口でも、新しい判断基準と発想を持って、有効な与信管理がもっと実現できるよう対処していって頂きたいと強く願う。
与信管理コンサル 髙見 広行