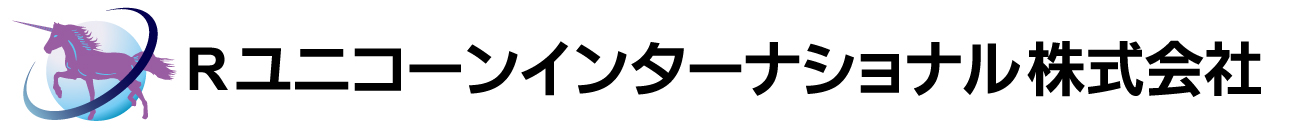小学校の卒業式 今昔物語!

一般的に日本では3月は別れの季節とも言われています。そしてこの別れとは、旅立ちと新たな出会いの意味が込められています。
先日、私の娘が通う小学校の卒業式に父親として参列して参りました。
自宅から徒歩圏内の学区内の公立小学校であり、私もかつて藤沢市内にある八松小学校という小学校に通っておりました。
数年前に、久々にその母校の八松小学校を訪れ、時代の流れを感じたところでした。校舎の建て替えもありグラウンドの場所も変わっていましたが、体育館とプールの場所はそのままでした。そうです。卒業式が行われた体育館が、同じ場所に残っていたのでした。物凄く懐かしかったですね。
さて、今も昔も変わらないのは、国歌斉唱、卒業証書授与、校長式辞、校歌斉唱といったところでしょうか?同時に、起立、礼、着席といった号令と共に、機敏に動く軍隊の訓練のように見えた生徒達の姿ですかね?
他方で、門出の言葉の披露の仕方、最後に卒業生がみんなで歌う歌のセレクションは時代の違いを肌で感じます。
今回式次第を見て、伝統的な儀式としてプログラムの中に必ず見受けられた、在校生代表の送辞と卒業生代表による答辞がないことに気付きました。その代わりに、卒業生みんなで分担する共同作業の形で順次発声していく場となった「門出の言葉」という形で、上手く継承されていました。しかも、その延長線で卒業生全員が一緒に歌う場面に繋がっていくのでした。演出としてはこちらの方が素晴らしいと心底思いました。
もはや、「蛍の光」とか「仰げば尊し」ではないんですね?そこは隔世の感を感じつつ、終始明るい雰囲気に包まれ、涙を見せる生徒も少なかったのも現代の卒業式の特徴なんですかね?
そして、もう一つ、和服(女子生徒の袴姿)の装いの卒業生が圧倒的に目立ったことでした。うちの娘もその流れに乗り、袴をレンタルしました。
在校生からのエールを受けて、また小学校生の生徒達が1年入れ替わっていく。この繰り返しの中で、小学校は一つの歴史を作っていくのだと思います。
娘の姿を記録に残すべくビデオカメラを手に、最後は家族や友達と一緒に写真撮影に応じている成長した娘の姿を目にして、一言、父親から「送辞」を送らせてもらいます。
「今後、山あり谷あり、人生には色々なことがあると思うけど、どんな出来事にも自分にとって何か意味があるもの、と受け止めて、謙虚に真っ直ぐに生きていって下さい。そして、願えば必ず夢が叶う、そう信じて、唯一無二の自分の人生を作っていって下さい。」
リスク管理コンサルの父親より