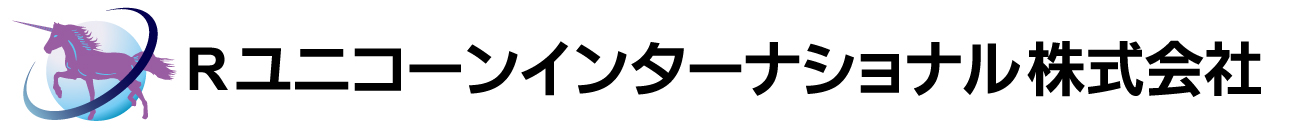ドビュッシーの魅力に惹かれて(今年への想い)


昨年の2024年ほど時間の経過を特に速く感じた年はありませんでした。年初の元日夕刻に起きた能登半島地震から始まり、いきなり新年のお祝い気分も吹っ飛んでしまいました。1日も早い完全な復興が実現することをただただ祈るしかありません。
さて、今年2025年の初っ端の投稿がまさかこの表題になるとは全く予想しておりませんでした。本当は大晦日に投稿すべく準備していたのですが、時間が確保できず、年明けでの投稿になってしまいました。今年もどうぞ宜しくお願いします。
現在も筆者タカミンは、継続してピアノのレッスンに勤しんでおります。一向に上達しないのは日頃の練習不足もありますが、言い訳がましいことを申し上げますと集中してレッスンの時間確保ができない現状もあります。
さて、現在タカミンが取り組んでいる曲は、何とあのテレビコマーシャルでも度々取り上げられている有名な旋律の、フランス人作曲家ドビュッシーの「月の光」です。ドビュッシーは「印象派」に属し、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した、音楽史上重要な作曲家の一人です。この曲は“ベルガマスク組曲”の第3曲で、月夜の情景及び心理を描写した秀作と高く評価されています。
因みに、拍子は八分の九拍子。また調も、「変ニ長調」という、あまり見ない調性です。これは、「ハ長調」という、ピアノの白い鍵だけでドレミファソラシドを弾ける、基準となる調からなんと「半音」高いだけの調なんですが、このキーが半音だけ高いせいで、フラット記号「 ♭ 」が五つも付いてしまう為、黒い鍵がやたら多用されることになる、特異な調と言えます。その意味で、非常に弾きづらい曲ですね。
かつて、どうしても一度弾いてみたい曲として、あの古典派の代表格であるベートーヴェン作曲の「月光第一楽章」がありましたが、今回はそれに準えて、ピアノの先生から提示を受けたのがこの曲でした。勿論、今まで一度も弾いたことのない作曲家ですが、現在娘が練習に取り組んでいるのが、同じくドビュッシー作曲の「アラベスク第1番」ということもあり、親子で一緒にチャレンジ的な要素もあって、この難曲に取り組んでおります。
さて、「月の光」ですが、皆さんはこの曲をただ聴いている分には、結構簡単に誰にでもすぐに弾ける曲ではないか?と思われる方も多いと推察します。確かに旋律は、単調かつゆったりとした綺麗なメロディーで、途中よりハープで奏でるような音色も登場してきて、終始ソフトな印象で、リラックスできる曲です。魅惑的かつ幻想的な世界が眼前に広がってくる、そんなイメージを抱かせる、とても魅力的な曲ですね。
が、しかし、実はこの曲は、特に私のような技術レベルの者に対しては、演奏者泣かせの非常に高度なテクニックを要する難解な曲でもあります。上記でも調に触れましたが、あまり見慣れない「変ニ長調」という長で、フラットが5つという、黒鍵を多用する曲で、譜読みにも非常に手こずります。
今年の夏には、2年ぶりに、娘との親子連弾ショーのイベントを開催すべく企画しておりまして、今年のテーマは間違いなくドビュッシーになります。娘の成長と共にこれまで開催してきたこのプライベートイベントも、だんだんと娘が大きくなるにつれて、中々こうして一緒に鍵盤に向き合うこともなくなってくるのではないかと感じています。少し寂しい気持ちはありますが、致し方ありませんね。
連弾曲は、別途、あの「美女と野獣」にチャレンジする予定ですが、これとは別に、ドビュッシーの曲で連弾曲を弾くことも検討中です。それよりも何よりも、とにかく、父親である私が「月の光」の演奏を完走させることが、目下の最大の課題です。果たして間に合うかどうか分かりませんが、弾けるところまで弾くということで、ベストは尽くしたいと思っております。
ショパンも相当難易度の高い曲だったのですが、更にまた今回のドビュッシーは、曲の趣向の異なる異次元の曲というのが正しい表現でしょうか?
今後も地道に生涯の趣味の一つとして、ピアノとは付き合っていきたいと考えており、ドビュッシーとの出会い・遭遇は貴重な経験になっています。
ピアノを生涯の趣味とする経営コンサル 高見 広行