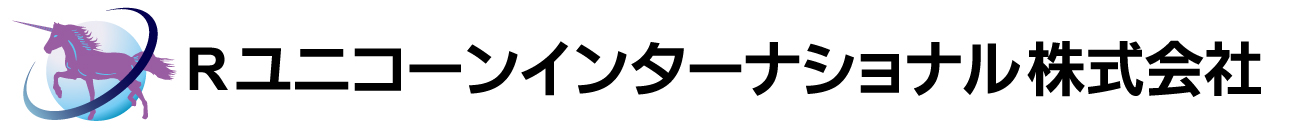取引先検討会(与信レビュー会議)の開催方法をアドバイスします!
皆さんの会社様では、定期的に自社の取引先をレビューする機会をきちんと設けておられますか?
人間の健康診断同様、取引先に対しても定期的な信用度のチェック・レビューが必要だということです。
ここで言う取引先には、販売先だけに限らず、仕入先や在庫の置き場となる商品預け先の寄託先も含まれます。所謂全取引先です。
通常、取引先レビューの機会は、原則、年に一度、各社別に与信限度を更改するタイミングで行うのが通常のスタイルです。各社様の社内ルールに従い、定期的に見直しを行う作業であり、営業マンの皆様にとっては手間暇の掛かる作業に思えるでしょうが、重要なプロセスだと認識しています。
他方で、今回皆さまに逢えてご案内するのは、取引先の内、全社全体で、あるいは各営業部署毎に、「問題先」を予め10社〜20社程度ピックアップし、それらの取引先に対して、与信管理担当部署との間で意見交換・討議を行う場となるのが、取引先検討会(与信レビュー会議)になります。
「問題先」についての選定基準は、予め社内で決めておかれる必要があります。通常では、信用度の低いかつ取引額の大きい先から順にセレクトしていくべきと考えます。営業部署側の出席者は、担当者とライン長で、 場合により上席者(決裁者)を含む場合もあります。また、社内に与信管理担当部署が存在しない場合は、コーポレート側の管理部署(経理課や総務課等)の方が出席し、更にグループ会社に属するケースでは、親会社の与信管理担当部署の方にも陪席して頂くと良いと思います。
会議の所要時間は、1社につき10分〜15分程度で、仮に10社とすれば最大2時間位が妥当なイメージです。従い、それ以上問題先がある場合は、部署毎に分けて開催するか、2部制にして、120分を2回開催するイメージとなります。
開催頻度は、最低年に1回、可能であれば、半年に1回の開催が望ましいです。
事前の準備は大切ですが、あまり会議資料の作成に負担が掛かり過ぎないように注意しなければなりません。取引先検討会の為に事前に用意する資料は、原則1枚のシートに各社別のデータが羅列されるように纏め、そのシートに一覧性を持たせることが重要です。
議事録の作成はマストですが、その土台になるのが、上記シートであり、そのシート上の一番右側に、必ず「結論の欄」を設けて、取引先検討会で討議した結果を記録として明確に残すようにして下さい。例えば、取引継続方針、但し決算書の直接取付に引き続き努める、又は、取引撤退方針(新規成約停止)などです。勿論、議論持ち越し(ペンディング)もあって然るべきです。
この会議のファシリテイターの役割は極めて重要であり、基本的にはコーポレート側の責任者の方が音頭を取るのが望ましいスタイルです。
各取引先についての営業部署の見方・印象等を聞き出す場であると共に、大いに議論を戦わせる場であることを決して忘れてはなりません。発言の際には遠慮は一切不要であり、自分の思っていること、考えていることを素直に表明することが肝要です。
通常のケースでは、営業部は取引を継続して行いたい、増やしたい、と思っているのに対して、審査部署側は、リスクに歯止めを掛けたい、その取引を止める方向に持っていきたい、と思うのが常です。
大事なのは、問題先に対して、会議の参加者全員が議論に積極的に参加し、意見を真剣に戦わせ、互いの立場を尊重しつつ、一つの結論を導き出すべく努力をするということです。

最後に、この会議においては、対面(面着)での打合せが効果的だと考えます。已むを得ない事情によりオンラインでの参加もありだとは思います。ただ古い考え方に聞こえるかもしれませんが、会議参加者の相手の顔と発言を生で見て感じて、それに対して自分の意見を率直に述べることこそが、この会議の重要な意義であると考えており、可能な限りリアルでの参加を切に希望します。
与信管理コンサル 髙見 広行